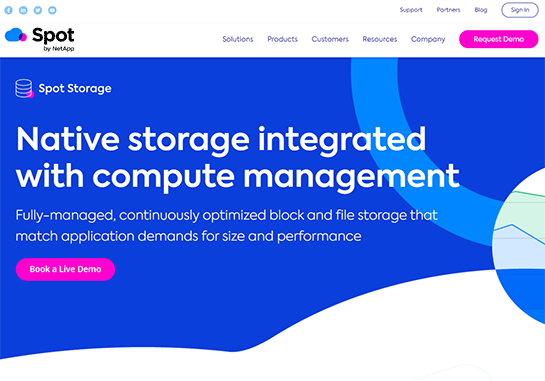サーバレスの次は「ストレージレス」の実現へ。NetAppがストレージレスを実現する新サービス「Spot Storage」を発表
AWS Lambdaなどに代表される「サーバレス」(Serverless)とは一般に、サーバがないのではなく、サーバの準備や管理が不要なことを指します。
つまり、アプリケーションを実行するためにサーバをプロビジョニングしたり、アプリケーションの負荷に合わせてサーバを増やしたり減らしたり、落ちたサーバを復旧させるといった作業が自動化され、サーバの準備や運用管理が不要であるのが、サーバレスの意味するところです。
NetAppは、このサーバレスの考え方をストレージにも適用し、ストレージの準備や運用管理を不要にする「ストレージレス」(Storageless)をクラウド上で実現する新サービス「Spot Storage」を発表しました。
Spot StorageはAWS、Microsoft Azure、Google Cloud上でNetAppが提供するクラウドサービス「Spot」により提供される予定です。
ストレージの準備も管理も不要、大きなコスト削減効果も
サーバレスでアプリケーションの負荷に合わせてサーバ数が増減するように、Spot Storageでもストレージがアタッチされる仮想マシンやコンテナが要求されるストレージ性能とストレージ容量に応じて、自動的にストレージの性能と容量が増減するようになっています。
これにより、あらかじめ管理者が必要な性能と容量を見積もってSSDやHDDなどの適切なストレージをプロビジョニングしておく、といったことが不要になります。
ストレージのプロビジョニングや管理が不要になるだけでなく、つねに必要最低限の性能と容量を持つストレージリソースが動的に割り当てられる仕組みのため、例えばストレージへの高速なアクセスが必要な時だけ高価なSSDが割り当てられ、アクセスがなくなれば性能の低い安価なストレージへと自動的に切り替わるといったストレージコストの最適化も行われます。
NetAppは最大で70%ものコスト削減効果があると説明しています。
シンプロビジョニング、重複排除、階層化などを組み合わせ
Spot Storageがどのような仕組みなのかを示したのが下記の図です。シンプロビジョニング、圧縮、重複排除、ストレージ階層化の技術を組み合わせていることが示されていますが、これらの技術をどのタイミングでどのように組み合わせているかまでは同社は明らかにしていません。
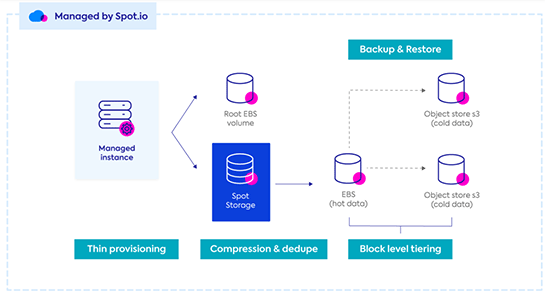
シンプロビジョニングとは、物理的なストレージ容量にかかわらず論理的なストレージ容量を大きく見せる技術。
圧縮と重複排除はデータを圧縮する技術、ストレージ階層化は性能の異なるストレージを組み合わせ、頻繁にアクセスされるデータだけを高速なストレージへ配置することで、ストレージコストを下げつつストレージ性能を向上させる技術です。
おそらくは、シンプロビジョニング技術を用いて小容量の高速なSSDを大容量に見せつつサーバにアタッチし、ストレージ階層化によって裏に大容量のストレージを配置。
高速なストレージと大容量の低価格ストレージを負荷によって動的に組み合わせつつ、圧縮と重複排除によって小さくしたデータを動的に再配置することで性能を最適化する、といったことを行っているのではないかと推測されます。
NetAppが買収したSpotと組み合わせる
Spot Storageは、NetAppが昨年買収したSpot(旧SpotInst)のサービスである「Spot」と組み合わせることが前提となっています。
Spotとは、簡単に言えば仮想マシンを自動的にプロビジョニングしてくれるサービスです。しかも可能な限り安価なスポットインスタンスから割り当ててくれるのが大きな特徴です。
アプリケーションの負荷に応じて仮想マシンを増減させる「Elastigroup」機能と、コンテナを増減させると同時にその基盤となる仮想マシンも自動的に増減させる「Ocean」が代表的なサービス。
どちらもSpotが仮想マシンを準備し管理してくれるだけでなく、可能な限り安価なスポットインスタンスから割り当ててくれるため、仮想マシンにかかるコストも非常に安くなるというものです。
スポットインスタンスは安価な半面、クラウドによって自動的に停止されてしまう場合がありますが、Spotはその際のフェイルオーバーも行ってくれます。
このSpotのどちらとSpot Storageを組み合わせるかによって、仮想マシン向けの「Spot Storage for Elastigroup」と、コンテナ向けの「Spot Storage for Ocean (Containers)」の2つのサービスが用意されています。
特にコンテナ向けのOceanは、コンテナベースであることと負荷によってコンテナ数が自動的に増減し、そのことを管理者が意識する必要がないことなど従来のいわゆる「サーバレス」なプラットフォームの要素を備えています。
NetAppでは、このサーバレスプラットフォームとしてのOceanと組み合わせた「Spot Storage for Ocean」をこそ「ストレージレス」を実現するものだとしています。
ストレージ分野での抽象化技術に期待
コンピュートの分野は仮想マシン、コンテナそしてサーバレスと使い勝手と抽象化が進んできましたがストレージの分野はコンピュートほどそうした進化が見られませんでした。
そうしたなかでNetAppが提唱するストレージレスは、これまでのさまざまなストレージ技術の蓄積を持つストレージベンダでなければ実現できそうにない、非常に面白い発想と技術ではないかと思います。
あわせて読みたい
QUICとHTTP/3がIETFのラストコール。RFCによる標準化が間近に
≪前の記事
セイコーが閉域網で正確な時刻を提供するNTPサービス「セイコークローズドモバイルNTP」発表。±50msec以内の正確な時刻同期を実現